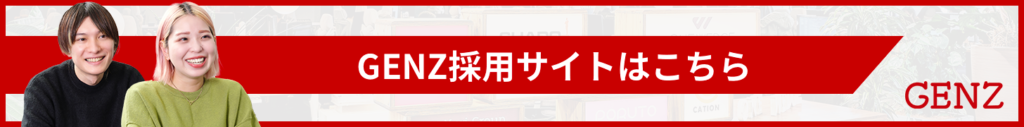私が1年間で学んだことは多い。
その中でも新卒社会人の普遍的な学びに過ぎない内容については省略させていただく。
本ブログで記載する特異な学びは、過去の自分と今の自分を比較したときに一番成長を感じたものとする。
主に2つ、「対人関係の重要性」「『QA』エンジニア」である。
これらの2つの学びについて記載する。
「対人関係の重要性」
大学時代、いくつものコミュニティに関わり、バイトも掛け持ちしていた。
転勤の多い家庭で育った影響もあって、人と関わることに慣れていたし、交友関係も広かった。
自然と、自分はコミュニケーションが得意なほうだと思っていた。
社会に出ても、人間関係には苦労しないと信じていた。
しかし、現実は少し違っていた。
入社してすぐに感じたのは、周囲との熱量の差。
どれだけ自分が頑張っても、誰かの低い温度が気になってしまう。
今思えば、それは完全に“他者比較”だった。
自分と他人を比べては勝手にモヤモヤして、理想とのズレに感情的になる。
知らず知らずのうちに、自分と他人を対比をしていたのだ。
そして、その気持ちはやがて職場の空気にも、自分の表情にも、じわじわと染み出していった。
比較することで相手に妥協できなくなり、自分にも余裕がなくなった。
そしてその小さな歪みは、やがて職場での関係にも滲み出ていった。
変わるきっかけをくれたのは、配属先の先輩たち。
彼らが共通して教えてくれたのは、“他者比較”をやめるということ。
誰かと比べて焦っても意味はない。
昨日の自分より、ほんの少しでも前に進めればそれでいい。
あくまでも評価軸は自己評価。
ただ、他者とは「良好な人間関係を構築しつつ、他人は他人とある意味で切り捨てる」関係性が一番重視するべきポイントである。
あの頃の自分は、ただ焦っていた。
早く認められたくて、評価されたくて、周囲に敏感になりすぎていた。
今も成長したい気持ちは変わらないが、少し冷静になれたことで、視野が広がった。
別の案件で、かつて同じチームだったメンバーと再び関わることになった。
そのとき気づいたのは、他者比較を手放したほうが関係はうまくいくということ。
比べずに接することで、助け合えるし、頼られることもある。
そんな関係が、自分の安心になり、仕事のやりがいにもつながっていく。
他者比較をやめることは、諦めでも妥協でもない。
それは、自分らしく働くためのひとつの選択。
そして、人と信頼を築くうえでの土台。
仕事も人間関係も、正解なんてない。
でも、「こうでなければ」と自分や他人にプレッシャーをかけすぎないことで、ふっと軽くなる瞬間がある。
今でも私は成長したいし、前に進みたいという気持ちは変わらない。
けれどその歩幅は、自分のリズムでいい。
他者比較に振り回されない日々は、思ったよりも穏やかで、じんわりと心地よい。
そして今、その穏やかさの中に、もうひとつの確かなテーマを見つけようとしている。
信頼を築くことで得られたこの関係性を、自分の中だけに留めておくのではなく、周囲へ、そして組織全体へと波紋のように広げていきたい。
それは、学びや気づきを「継承」していくという意識。
関係を築き、文化をつくることが、仕事の一部になっていく。
今後GENZメンバーが増えたとき、自分はどう在るべきか。
その問いに対するひとつの答えが、「自他共にプラストリガーとなるスタンス」。
この先に向き合っていく「QAエンジニア」という仕事と重ねながら、ただ成果を出すだけでなく、周囲の誰かにとって前向きなきっかけになれるような働き方を選んでいきたい。
「『QA』エンジニア」
様々な案件を経験する中で、自分の取り組み方に疑問を感じた瞬間があった。
このままでいいのか。この仕事の価値は、どこにあるのか。
職種は「QAエンジニア」。Quality Assurance──品質“保証”を担う職種であり、似た言葉に“品質管理”がある。
QC(Quality Control)が製造段階での品質を管理するのに対し、QAは出荷後までを含めた全体の品質を保証する。
つまり、より広い時間軸とビジネス全体を見据える立場が、僕たちQAエンジニアの役割になる。
そして「品質」という言葉そのものも、時代とともに意味を変えてきた。
当初は「管理」視点での品質だったものが、やがて「監査」や「保証」の必要性が高まり、それを体系化・国際標準化したものが、今のQAにつながっている。
けれど、それだけの歴史と概念があるはずのQAという職種が、現場でどうやって品質を“上げて”いるのかと考えると、まだ輪郭が曖昧に感じる。
というのも、テストの現場では「システムが動くか」を目的化しているテストもある。
アプリケーションそのものも、特段新しい技術を用いたものではない。
ユーザビリティに欠けたままリリースされるプロダクトもある。
資本主義のスピード感やアジャイル開発の潮流の中で、まずは“動かす”ことが最優先されているケースもまだまだあり、「品質」は二の次に追いやられている印象も少なくない。
そうした中で、テストだけに目を向けていては限界がある。
求められるのは、QCD(品質・コスト・納期)の視点。
僕たちQAエンジニアは、ただのテスト実行者ではなく、プロダクト全体の品質を意識した“ビジネスの当事者”でなければならないと感じた。
この在り方を実現するには、開発会社との信頼関係も欠かせない。
だからこそ、ここまで綴ってきた「対人関係の重要性」は、単なる人付き合いの話ではない。
対人のあり方が、最終的にプロダクトの品質へとつながる。
それを体現することこそが、「QAエンジニア」としての本質だと考えている。
この2つの学び──人との関わり方と、品質への向き合い方。
これが、今の自分を形づくっている軸になる。
2年目以降も、この気づきを土台にしながら、新たな問いと学びを見つけていくつもりだ。
<過去の記事>
【新卒ブログ】新卒エンジニア本を読まないことを辞めたい
【新卒ブログ】プログラミングから逃げたエンジニア-第2章-
【新卒ブログ】プログラミングから逃げたエンジニア(社会人編)
【新卒ブログ】プログラミングから逃げたエンジニアー第1章ー
【新卒ブログ】プログラムを書かないエンジニアとはー序章ー